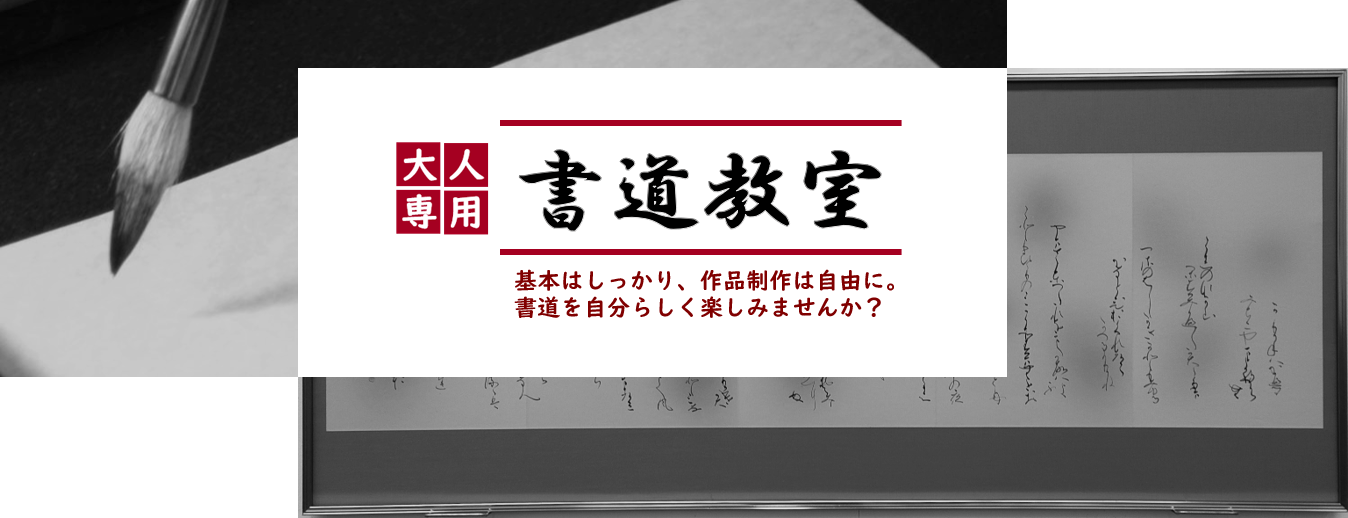クメールのほほ笑みに魅了
2025年10月の最終週、シェムリアップへ3泊5日の旅に出かけました。
雨季から乾季へと移り変わるこの時期、天候が少し気がかりでしたが、幸い雨に降られることもなく、現地としては過ごしやすい気候。まさに旅に最適な季節でした。
※ 本記事は書道とはあまり関係がありません。旅行記としてお楽しみください。
カンボジア(シェムリアップ)の基本情報
🙋🏽クメールとは
現在のカンボジアの大部分をしめる民族です。
また、カンボジアの公用語である「クメール語」や、カンボジアの文化や歴史全体を指すこともあります。
💰お金のこと
現地の通貨はリエル、1USドル=約4,000リエル。
とはいえ、観光地ではほとんどUSドルが使えます。
水2本で1USドル、ココナッツジュースも1USドル(1個で約1リットル)。
クメールマッサージのオプションは20USドルほどでした。
📝お土産やコンビニエンスストアでの物価は日本とあまり変わらない印象です。
💱両替と支払い
今回はパッケージツアーだったため、主な旅行費用はあらかじめ支払い済みでした。
現地での支払い用として、成田空港で2万円を128USドルに両替。
帰国時に残ったのは77USドルだったので、実際に使ったのは二人で51USドルほどでした。
カンボジアでは空港や一部のお店でクレジットカードが使えますが、
レストランでの飲み物やコンビニでの買い物にはUSドル紙幣を使用。
結果的に、旅のあいだの現金支出は二人合わせて1万円でお釣りが出る程度でした。
🌡️気温と服装
10月は雨季の終わり頃にあたります。
10月後半の気温は平均して最高気温が30℃前後、最低気温が24℃前後でした。日中は蒸し暑いため日本の夏の服装ですが、早朝などには薄手の羽織ものがあると快適です。
👄クメール語メモ
- こんにちは:スウォスダイ
- ありがとう:オークン
📝クメール語の発音は本当に難しいです。試しに自分の発音を翻訳アプリにかけてみると、言いたいこととはまったく逆の意味に変換されてしまうこともありました。
それでも、現地の方とのコミュニケーションには、ガイドさんに教えてもらったこの2つの言葉だけで十分でした。その他のやり取りは、意外と英語でなんとか通じます。
1日目:成田からシェムリアップへ
成田空港を午前9時過ぎ発のフライトで、経由地ベトナム・ホーチミンへ。
激しい雷雨の影響で、乗り継ぎ便が1時間半ほど遅延、シェムリアップ着は夜の8時過ぎ(ベトナムとカンボジアは日本から2時間遅れ)。
シェムリアップ空港では、ガイドのSさんが笑顔で出迎えてくれました。ホテルへ向かう車中では、穏やかでユーモラスな語り口で現地の話をしてくれ、すぐに打ち解けることができました。
2日目:アンコール・トムとトンレサップ湖 ― クメールのほほえみに出会う

遺跡観光は、3日間有効のアンコールパスポート(顔写真入り)の購入から始まりました。
アンコール・トム
おすすめ度
… バイヨン寺院が補修中で見学できなかった分マイナス1
“アンコール”は「都」、“トム”は「大きな」という意味。
800年前、アンコール王朝の最盛期の王・ジャヤヴァルマン7世によって築かれた城郭都市で、一辺3 kmの正方形をしています。城壁内には中心寺院のバイヨンをはじめ、大小さまざまな遺跡が点在しています。


まずは、ピンク色が鮮やかな睡蓮が浮かぶ外堀を、ゴンドラに乗って遊覧。水辺では結婚式や家族写真を撮る現地の人々の姿も見られました。


次に参道へ。南大門へと続く橋の両サイドには、左側に神々、右側に悪魔の像が並び、ナーガ(蛇神)を綱引きするように持っています。一体一体の顔がすべて異なり、表情の豊かさに驚かされます。
南大門は車がその下を通り抜けられるようになっています。
バイヨン寺院


アンコール・トムの中心にあるバイヨン寺院は、巨大な観世音菩薩の四面像で有名。12世紀末に建てられた仏教寺院。
第一回廊には当時の人々の営みが詳細に描かれたレリーフ。
- チャンパ(ベトナム)軍との戦いに向かうクメール軍の行進
- 従軍する家族。炊事をしたり、お酒を飲んだり、亀にお尻をかまれたり。
- 商売や狩り、食事の用意をする人々
- 水上戦では戦いに負けた人がワニに食べられたり、トラに襲われそうになって木の上に逃げる人
- 出産シーン
- 闘犬や闘鶏を楽しむ人々
などなど。この遺跡が面白いのは、宗教上の神話が描かれるのではなく、庶民の普段の様子が克明に描かれている点。緻密なレリーフはまるでビデオ映像のように当時の様子を伝えてくれます。じっくりレリーフと対峙していたら1日あっても足りないかもしれません。
残念ながら中央祠堂が修復工事中のため、第一回廊までしか見学できませんでした。あの有名な”クメールのほほ笑み”と称される有名な観世音菩薩を拝せずじまい。修復工事が終わったら、再び訪れたい場所です。
バプオーン(隠し子)


11世紀中頃に建てられたヒンドゥー寺院。
名前の由来は、王妃がシャム王の報復を恐れて子を隠したという伝説から。
空にかかる橋のような参道は、地上と天上とを結ぶ「虹の架け橋」とも呼ばれています。
ピミアナカス(天上の宮殿)

10世紀後半のヒンドゥー寺院。王が夜ごとナーギー神の化身である美女と会ったという伝説が残っています。
ライ王のテラス・象のテラス


「ライ王のテラス」は癩(らい)病にかかった王が隔離され、死後に祀られた場所。ライ王像の背後、ちょうど二人が立っているあたりに火葬場があったのだという。病に侵されつつもほほ笑みを絶やさない像からは、王の徳とそれを慕う民衆の心が表れていると感じました。
高さ約6 mのテラスは迷路のような通路に囲まれ、壁面にはおびただしい数のレリーフが。


12世紀後半につくられた「象のテラス」は王族が閲兵を行った場所。「勝利の門」からまっすぐに続くこの広場では、戦勝の儀式が行われたり、また近隣諸国の王を出迎えたという。
タ・プローム ― それはまさにラピュタ
おすすめ度
… 大木の根にからめとられた遺跡は圧巻!




12世紀にジャヤヴァルマン7世が母のために建立した仏教僧院。
カジュマルの根が遺跡を飲み込むように絡みつく光景は、まさに自然と人間の時間の交錯。
映画の舞台にもなった有名な遺跡です。
トンレサップ湖クルーズ
おすすめ度
… 遺跡見学から一服、涼風も。少年との交流が◎。優雅なアプサラダンスも必見!



東南アジア最大の湖、トンレサップ湖では、水上生活を送る人々の暮らしを見学。
船長の10歳ほどの息子さんが、乗客の案内から係留まで健気に働く姿が印象的でした。別れ際に合掌しながら「オークン」と挨拶すると、まぶしい笑顔が返ってきました。

夜はレストラン「アマゾン・アンコール」でクメール料理のビュッフェとともに、宮廷舞踊「アプサラダンス」を観賞。華やかな衣装と静かな微笑み、優雅な舞、クメール文化の一端を堪能しました。
3日目:アンコール・ワットに流れる時

アンコール・ワットの日の出
おすすめ度
… 朝焼けが見られなくて残念だった分マイナス1



朝5時出発。夜明け前のアンコール・ワットへ。
明け方に浮かび上がった寺院のシルエット、そして水面に映る姿は本当に幻想的。世界中から集まったたくさんの観光客と共に静かに一つの瞬間を待つという体験も興味深いものでした。
アンコール国立博物館
おすすめ度
… 音声ガイド付き、展示品や陳列は◎。アンコール・ワットのジオラマへの照明が常時点灯ではないためマイナス1


唇が厚いクメール像は、どこか日本の俳優・京唄子さんを思わせるとガイドさん。当時の王様をモデルにした像をはじめとするそんな像たちのご尊顔は穏やかで大変美しい。
ナーガ(蛇神)が仏の台座や光背になっている釈迦像は、日本の蓮華の台座に天界を思わす光背の釈迦像とは大きく違い、別物の印象。
遺跡では石造ばかりだが、ここでは小型中型の銀製や真鍮製の鋳造像も多い。ほとんどの遺物はガラスケースなしで展示されており、質感を間近に感じることができました。
お買い物とクメール料理
おすすめ度
… オールド・マーケットは好みが別れそうなのでマイナス1。お土産とクメール料理は◎
オールド・マーケット


アンコール遺跡を築いた人々の末裔たちが、今のカンボジアでどのように暮らしているのかを知ることも大切です。
地元の人々で賑わう市場では、果物や衣類、干し魚、干し肉が山のように積まれていました。熱気と活気と芳香で気圧されました。
興味深かったのは、トゥクトゥクやバイクに混じってレクサスやベンツも走る不思議な光景。
「高級車に乗るのは袖の下をもらう役人」とガイドさんが笑います。
ノム・トム・ムーンのお土産
地元の伝統菓子ノム・トム・ムーン をお土産に仕立てた、日本人オーナーのお店「カンボジアティータイム」でお土産を購入。きれいな店内、人当たり良く商売上手な店員さんに思わず笑顔に。
試食させてもらい、ビターチョコでコーティングされたカシューナッツやドライマンゴーも購入しました。
クメール料理の昼食



青パパイヤのマリネの前菜に辛くない香辛料が香る焼き鳥、揚げたライスペーパーの器にウリが入った酢豚。どれも初めての味なのに、どこか懐かしい。脂っぽくなく、さっぱりしていて食べやすかったです。
アンコール・ワット再訪
おすすめ度
… 見どころ満載、文句なしの満点!

“アンコール”は「都」、“ワット”は「仏教」という意味。
12世紀前半にスールヤヴァルマン二世によって創建されたヒンドゥー教寺院。ここには4つの回廊があります。
第一回廊

1番外周が第一回廊、マハーバーラタ、ラーマーヤナといったヒンドゥー教の物語を題材とした壮大なレリーフが続きます。
十字回廊


ここには1632年に訪れた平戸藩士・森本右近太夫による墨書(落書き)も。当時の日本人はアンコール・ワットを祇園精舎と思い込んでいたとのこと。
胸をたたくとボワンと響く空間も。よく響けば健康なのだとか?
第二回廊


第二回廊の外壁では、装飾的な衣をまとった女神デバターたちが微笑んでいます。遺跡の像たちは男性も女性も上半身は裸で風邪をひいてしまいそう。
第三回廊



第三回廊は高さ65 mの中央祠堂を有する最も高い場所にある。中央祠堂にはヒンドゥーのデバターに囲まれた仏陀像が安置。お供え物やお線香が供えられていて今でも信仰の対象。往時は王様しか見ることができなかった風景を、現代ではだれでも観賞できるとはありがたいことです。



回廊から出てくると夕日の時間。素晴らしいサンセットと共に眺める遺跡はまた格別。
朝日と夕日、自然と遺跡の調和に2度も立ち会えるという、なんとも贅沢な体験でした。
夜はフランス料理の夕食と、クメール式マッサージで一日の疲れを癒やしました。
4日目:東洋のモナ・リザに会いに

朝8時出発。アンコール・ワットから北北東にバスで40〜50分。
郊外では放牧された白い牛や、水辺に集う水牛の群れ、放し飼いの犬、鶏と、動物たちの姿をよく見かけなごみました。
田舎道はアスファルト上の泥が固まっていて、とにかく跳ねる。運転手さんが丁寧によけながら走ってくれているのにロデオ状態。途中で小雨が降りましたが遺跡に着くとまもなく止みました。
この日訪れた遺跡はどこも観光客はほとんどおらず、独り占めできました。
バンテアイ・スレイ ― 東洋のモナ・リザと対面
おすすめ度
… 小さい遺跡に凝縮された精巧なレリーフに目を見張ります!







“バンテアイ” は「砦」、“スレイ” は「女性」を意味し、9世紀後半に当時の高官によって建てられたヒンドゥー教寺院。
この遺跡は意外なほど小さくこじんまりとしている。しかし、レリーフの精巧さは群を抜いている。さらに鉄さび色に赤茶けた遺跡が、雨に濡れたおかげで一段と際立つ様子は異彩を放つ。
特に「東洋のモナ・リザ」と称される女神像は必見。
中央祠堂の入り口両サイドのレリーフには美しいデバターや男性神が粒ぞろい。それぞれに個性があるためここへ来たら是非お気に入りを見つけてみて。
ただし、これらレリーフにはロープが張られて近づくことができないため、双眼鏡は必須です。
ロリュオス遺跡群
おすすめ度
… 歴史的には面白いのだが、似たような遺跡たちに少し新鮮味が薄れてしまったためマイナス2。
アンコール中心部から南東に20 kmほど離れており、観光客もまばら。
9世紀後半に建立された、アンコール・ワット以前の遺跡群です。
ロレイ


レンガ造りの古い寺院。アンコール・ワットの原型といわれます。
プリア・コー(聖なる牛)



名前の通り3体のナンディン(牛)の像が。
インドラヴァルマン一世が父母と祖父母を祀るために建てたいわばお墓。祠堂は計6基、手前の3基が先王である父とその両親、奥の3基が母とその両親のものだという。
実は私、霊感はないと信じていますが、たまに旅先で不穏な気配を感じることがあります。今回、祠堂の間を歩いているとき、同種の薄気味悪さを感じました。何かあるのでしょうか。。
祠堂の手前、脇には火葬場とした建物も。
バコン



ロリュオス遺跡群の中では最大の遺跡。
最初期のピラミッド式寺院で、後にアンコール・ワットを建てたスーリヤヴァルマン2世によって修復。
基壇には象の像が並んでいたり、楼門の破風から中央祠堂の屋根を額縁のように切り取れたり、第五層の壁画には6人の阿修羅が神と争うレリーフが残っていたり、と見どころが多い。
帰国の途
夕方、シェムリアップ空港へ。
ホーチミンで再びフォーを味わい、深夜便で帰国。
翌朝8時半に成田到着。新品のトランクに小さな穴が開いていましたが、それも旅の証のひとつです。
✈ 旅を終えて
アンコールの遺跡群は、神秘的な石造建築というだけではなく、祈りと時間の重なりそのものでした。
自然とともに在る遺跡、人々の穏やかな笑顔、そしてクメールの美意識。
この旅で感じた穏やかさと力強さ、そして何より人々の気配りとほほ笑みはとても印象的でした。
アンコール遺跡とマヤ遺跡との共通点
旅の予習としてガイドブックを見ていた時から気になっていたのは、アンコール遺跡とマヤ遺跡がよく似ている点です。
人物やその髪型、また人物を横からとらえたアングルなど、マヤ遺跡かと見紛うレリーフが数多くあります。
また、ピラミッド式の宗教施設の類似。
例えばピミアナカスはマヤのチチェン・イッツァーの階段型ピラミッドとよく似ています。このピラミッド式の建立年代も近く、最初期のバコン寺院が9世紀後半、一方のチチェン・イッツァーは9世紀前半です。
太平洋を挟んでいながら、似たような緯度の地域で似たような様式が発生したとは、とても興味深いです。
日本文化とクメール文化の感性の違い
余白や間を大事にする日本文化に対して、余白を恐れるクメール文化。この対比がとても面白かったです。
どの遺跡を訪れても、びっしりと彫り込まれたレリーフや装飾が目に飛び込みます。わずかな空間にも物語や神話が刻まれ、石の一面一面が語りかけてくるようでした。
一方、日本では「何も描かない」ことや「沈黙の美」を良しとする文化が育ちました。描かないことで想像を促し、間を置くことで心に余韻を生む。
同じアジアの中でも、表現の方向性がこれほどまでに違うことに驚かされます。
石に刻む民族と、紙に余白を残す民族。
クメールのレリーフの密度に触れながら、あらためて日本の「間」の美学を思いました。