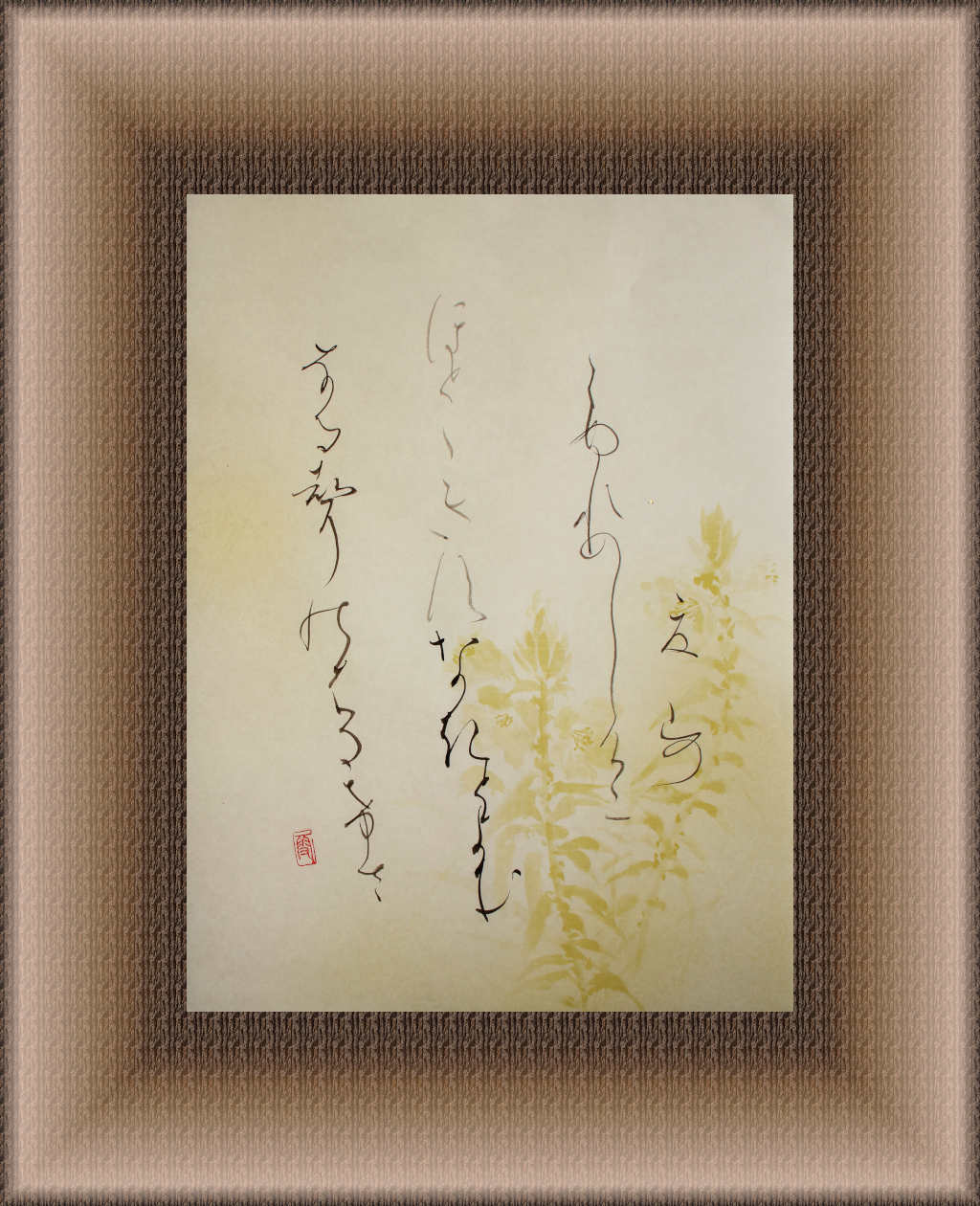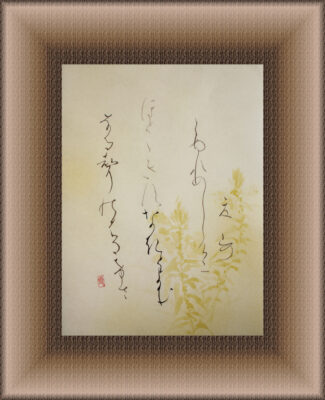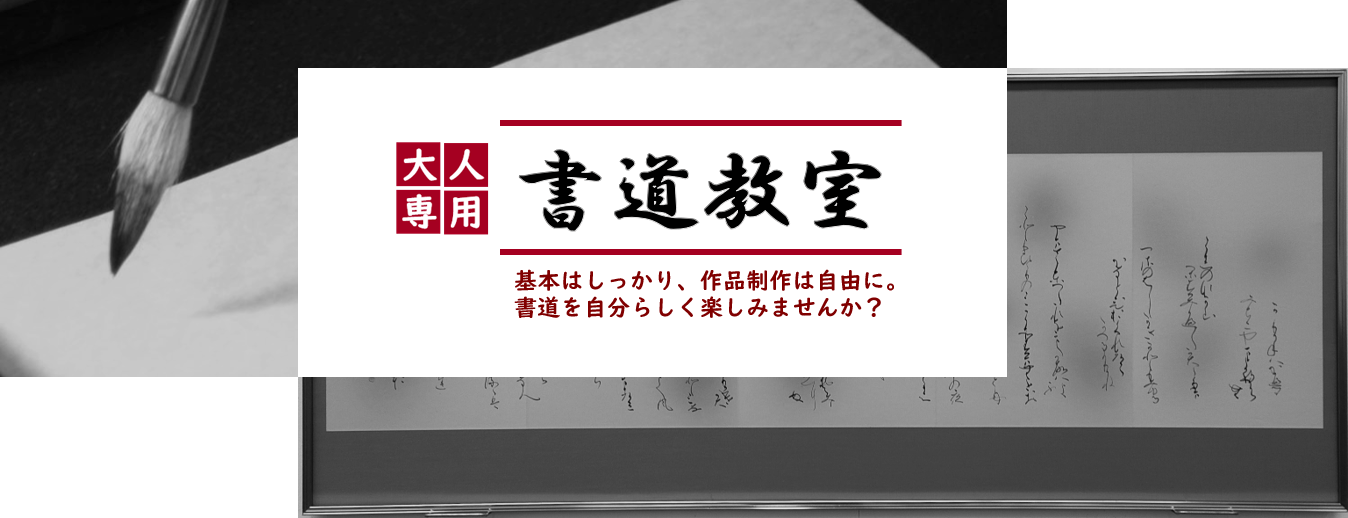#132 夏山の木末の繁にほととぎす鳴き響むなる声の遥けさ
| 作品サイズ: | 半紙 約33×24 cm |
|---|---|
| 仕立て: | 額装 |
どんなうた?
| しいか: | なつやまの こぬれのしげに ほととぎす なきとよむなる こゑのはるけさ |
|---|---|
| 詩歌: | 夏山の木末の繁にほととぎす鳴き響むなる声の遥けさ |
| 詠者: | 大伴家持(おおとものやかもち) |
| 歌集: | 万葉集 |
| 制作: | 759年以前 (同集成立以前) |
| 出典: | 新 日本古典文学大系1 岩波書店 |
夏山の梢の茂みでホトトギスが鳴いている。その鳴き響きわたる声のはるか遠いこと、といったかんじでしょうか。
よしなしごと
「響む」を読めましたか? 私は読めませんでした。
大辞泉によると平安時代の末ころまで「とよむ」、そのあとは「どよむ」と読むそうです。今回は万葉の歌なので「とよむ」が正解です。
このほかにも「木末」を「こぬれ」と読んだり、繁みを「繁(しげ)」としたり、今とは違う言葉遣いに古(いにしえ)を感じますね。